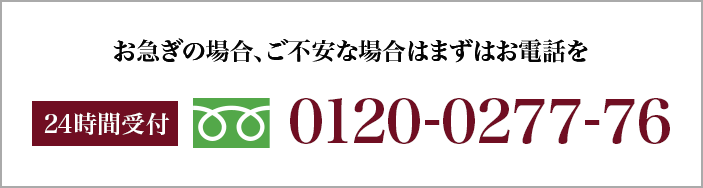多くの場合訃報は、ある日突然届きます。大切な人の死は大きなショックです。訃報を受けた場合、故人と最後のお別れをすることや遺族への弔意を表すという目的から、葬儀に参列することが一般的です。しかし、葬儀を行う場所が遠方である、健康状態が悪いなどの理由から、葬儀に参列できないこともあります。この記事では、そんな時の対処方法についてご紹介します。
葬儀に参列できない理由とは
葬儀に参列できない理由は多岐にわたります。一般的な理由としてあげられるのは地理的な制約で、遠方に住んでいるために時間的、経済的な事情から参列が困難な場合があります。
また、自身や家族の健康状態が参列を許さない場合もあります。長期にわたる病気や突然の怪我、感染症のリスクなどにより、葬儀への参列が難しくなることが考えられます。
さらに、仕事や家庭の事情で、スケジュールが調整できないという場合もあります。これは特に短期間でスケジュールを変更することが難しい職業に就いている人や、子育てや介護などの責任を負っている人に多く当てはまります。
新型コロナウイルスのような社会的な理由により、身体的な距離を保つ必要がある場合もあります。パンデミックの最中では、人々が集まる場所を避け、自己隔離が求められることがあり、今後も、このような理由で葬儀に参列できなくなる可能性は否定できません。
これらの理由はどれも、故人への敬意を欠いているわけではありません。それぞれの状況を理解し、適切に対応することが大切です。
葬儀に参列できない場合の基本的なマナー
葬儀に参列できない場合でも、故人に対する敬意と遺族への思いやりを示すための基本的なマナーが存在しますので、以下にご紹介します。
理由を適切に伝える
参列できない理由を伝えます。できるだけ早く、喪主や遺族に直接、または適切な方法で伝えるべきです。参列できない理由を簡潔に、しかし敬意を持って説明することが大切です。
その際の一般的な連絡手段は電話、メール、SNSです。最も確実な方法は直接会話できる電話ですが、葬儀の際のご遺族は忙しい場合が多いので、長話は避けましょう。メールやSNSで訃報連絡を受けた場合、特別な事情が無ければ、先方の連絡方法にならって返信すると良いでしょう。
供花・供物・香典を送る
供花や供物、香典を送付することで、参列できない場合でも故人への敬意を示すことができます。供花や供物は葬儀場所に直接送ることが一般的ですが、宗教、宗派、会場によって適する供花や供物が異なるため、葬儀を行う葬儀社に直接依頼することをおすすめします。
香典は現金書留で郵送することが可能です。ただし、香典の金額や香典袋の選び方、表書きの書き方などのマナーは、地域や宗教・宗派によって異なるため、マナーを守って準備することを意識しましょう。表書きや金額の目安については、こちらの記事で紹介しています。
【仏教・神道・キリスト教】香典袋の表書きや渡し方・金額の目安を紹介
香典を送る場合、香典を入れた香典袋だけを送ると味気ない印象を与えてしまう可能性がありますが、短い手紙を添えて送ることで、送り主の誠意や弔意を伝えることができます。手紙を書く際の注意点は、拝啓・謹啓などの頭語や時候の挨拶を書かないことです。また、故人の死因を尋ねることはマナー違反となりますので、そのような質問をしないように気をつけましょう。
弔意を表すためのその他の方法
後日弔問
葬儀に参列できなかった場合でも、後日弔問することは可能です。これは故人への敬意を示す重要な方法であり、遺族に対する深い弔意を示すことにもつながります。
後日弔問は、葬儀が終わってから数日から四十九日までの間が適切な期間といえるでしょう。突然弔問することはマナー違反となりますので、事前に遺族と相談し、日時をお約束して弔問しましょう。何らかの方法で事前に香典をお渡ししてあれば、お花やお菓子などの供物を、香典をお渡ししていなければ、香典を持参しましょう。
オンラインで参列する
一部の葬儀社ではリモート葬儀に対応しています。ZoomやSkypeなどのビデオ会議ツールを用いて、葬儀に「オンラインで」参列することが可能であれば、遠方にいても、体調がすぐれない場合でも、故人との最後の別れを温かく見送ることができます。
ただし、オンラインでの参列にもマナーがあります。「背景のノイズを減らす」「適切な服装を選ぶ」「カメラとマイクの設定を事前に確認する」など、故人への敬意と他の参列者への配慮を忘れないように参列しましょう。
まとめ
・地理的な制約や本人や家族の体調、仕事の都合など、様々な理由で葬儀に参列できない場合、適切な方法で葬儀に参列できない旨を伝える必要があります。
・葬儀に参列できない場合、供花や供物、香典を送って、故人への弔意や遺族への配慮を表すことが可能です。
事前相談、お葬式依頼は
群馬県桐生市周辺に9つの式場を完備する
あすかホールにお任せください。